 ピグマリオン 今しかできない幼児の算数シリーズ1 2才児のさんすう
ピグマリオン 今しかできない幼児の算数シリーズ1 2才児のさんすう
【対象年齢の目安:2歳〜】
画期的幼児教育法【ピグマリオンメソッド】を考案した伊藤恭先生が書かれた幼児教育本の隠れたロングセラー【2才児のさんすう】
「数は教えるものではなく学ぶものである」という伊藤先生ならではの教えが詰まった一冊で、幼児算数の指導書として多くの保護者様にご愛用いただいています。
本書の魅力は数教育にとどまりません。お子様の心も一緒に伸ばす教育書です。豊かな人格の上に数能力、思考力、想像力、言語能力が育ちます。
いまいちテキストでさんすうが理解できないお子様、指導方法に悩んでいるお母様。本書でもう一度、数の考え方を見直してみませんか。
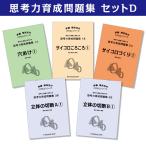 6歳児~ 思考力 パズル 思考力育成問題集 セットD
6歳児~ 思考力 パズル 思考力育成問題集 セットD
【対象年齢の目安:6歳児〜】
思考力育成問題集セットDは、立体図形をテーマにした思考力パズルで、「積み木推理」「立体認知」などの応用問題になります。いずれも、平面でなく立体的な空間をイメージすることで、高い空間把握能力が身に付きます。
●前後,上下,左右の3方向を同時に考える「穴あけ」
●頭の中のイメージ力を鍛える「サイコロころころ」
●サイコロの展開図を探す「サイコロづくり」
●最難関中学の入試問題でも頻出「立体の切断A」
●切断面の模様までイメージできるか「立体の切断B」
取り組む中で、「認知スキル」「概念化スキル」「論理スキル」が育ちます。
最初は初級編ですが、後半の問題は、大人でも読み切ることが難しい問題も含まれています。
ぜひ親子でチャレンジしてみてください。
【思考力育成問題集について】
ピグマリオンの数多くある問題集の中から、次世代スキルを伸ばす小学生向けの問題集をPYGLIシリーズとして選びました。
思考力パズルはルールだけ確認したら、あとは子ども自身が1人で考えて答えを出すことができるので、「1人でできた」という達成感が持てます。自信がつくので、難問に対して粘り強さ,集中力が身に付きます。
 知育玩具 シールブック おさるのジョージ まるまるシールはり 3歳 4歳 5歳 学研ステイフル
知育玩具 シールブック おさるのジョージ まるまるシールはり 3歳 4歳 5歳 学研ステイフル
【対象年齢:3歳〜】
世界中で大人気「おさるのジョージ」からシールはりカードが登場!
台紙とシールはパッケージの中に収納できるのでお片付けも簡単です。
パッケージにシールの使い方の説明付き
まるのシールをたくさん貼って8種の絵を完成させよう!
余ったシールも自由に貼って楽しめます。
対象年齢:3・4・5歳〜
【サイズ】
ケース:327×225×5mm
本体:210×270mm
【内容物・仕様】
8テーマ(貼る台紙8枚,シール14シート/490片)
穴あきOPP袋入
 知育玩具 シールブック おさるのジョージ シールはり 2歳 3歳 4歳 学研ステイフル
知育玩具 シールブック おさるのジョージ シールはり 2歳 3歳 4歳 学研ステイフル
【対象年齢:3歳〜】
世界中で大人気「おさるのジョージ」のシールブック
133ピースのシールを貼ってはがして自由に遊べる!
持ち運びしやすいA5サイズでお出かけにもぴったり!
再剥離可能な台紙で長く使って楽しめます。
同じ数になるように貼るなど知育要素も盛り込んだ内容で遊びながらおけいこもできます。
手先の器用さや創造力も養うことができます。
対象年齢:3・4・5歳〜
【サイズ】
パッケージ:215×183mm
本体:210×148mm
【内容物・仕様】
8ページ(シール6ページ/133ピース)
ヘッダー付OPP袋入
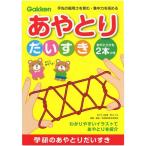 知育玩具 あやとりだいすき 3歳 4歳 5歳 学研ステイフル
知育玩具 あやとりだいすき 3歳 4歳 5歳 学研ステイフル
【対象年齢:3歳〜】
イラストが大きくて見やすく、わかりやすく手順を説明する工夫がたくさん盛り込まれた学研の幼児能力開発シリーズの「あやとり」
あやとりで楽しく遊びながら、想像力・集中力・空間認知力を育てます
説明はひらがなで記載されているので、小さなお子さまでも自分で読んで取り組むこともできます
収録作品は4項目22種類
やさしい・ふつう・むずかしいの3段階の難易度に分かれています
すぐに遊べる結び目のない紐2本つき
【サイズ】
本体:W182×H257mm(B5サイズ)
【内容物・仕様】
本文/36ページ・全22種類
あやとり紐2本(Φ3mm×1370mm/ナイロン製)
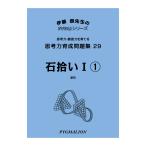 思考力パズル 思考力育成問題集29 石拾いI(1)
思考力パズル 思考力育成問題集29 石拾いI(1)
【対象年齢の目安:6歳〜】
ー縦、横、ななめの動きを頭の中でイメージする「石拾いI」ー
矢印のところから進んで石(○)を拾い、残った数を答えるというシンプルなルールです。直線やレ点をかきこまず、できるだけ頭の中で考えることで認知スキルが育ちます。部分ではなく視野を広げて全体に注目し、石(○)の数は数えずにまとまりでとらえるようにしましょう。
取り組む中で、「認知スキル」が育ちます。
【思考力育成問題集について】
ピグマリオンの数多くある問題集の中から、次世代スキルを伸ばす小学生向けの問題集をPYGLIシリーズとして選びました。
思考力パズルはルールだけ確認したら、あとは子ども自身が1人で考えて答えを出すことができるので、「1人でできた」という達成感が持てます。自信がつくので、難問に対して粘り強さ,集中力が身に付きます。
最初は簡単なので、何となくの感覚でも解けますが、後半の問題は、大人でも読み切ることが難しい問題も含まれています。
ぜひ親子でチャレンジしてみてください。
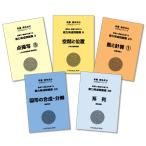 5歳児 幼児 ドリル 能力育成問題集 セットC
5歳児 幼児 ドリル 能力育成問題集 セットC
【対象年齢の目安:5歳〜】
●ひらがな,カタカナの読み書きの前にまずは「点描写3」
お手本通りに描き写す点つなぎの問題です。「注意力」「構成把握能力」など、知能の発達段階をチェックできるため小学校入試でも頻出単元です。
●3次元空間把握能力を身に付ける「空間と位置」
「左右判断」「光の方向」「風向き」「鏡絵」「水面」「後ろ姿」など様々な問題が出てきます。3次元空間である日常生活を通じて、問題の意味を理解していきましょう。
●図形のセンスを鍛える「図形の合成・分解」
図形能力は後天的に育つ能力で、小学校入試だけなく中学校入試にも役立ちます。また、ペーパーだけでなく「マグ・プレート」などの学具と合わせると効果的です。
●規則性や法則性を発見する思考力が育つ「系列」
この分野の問題は、知識があっても答えられません。まずは、問題の意味を理解し、そこから法則や規則を発見する必要があるため、思考力の基礎を鍛えられます。
●まずは数の仕組みを理解しよう「数と計算1」
本来、数は1,2,3,…と数えるのでなく、瞬時に数を2〜5のかたまりに分解して数をまとまりとして考えるものです。小学校の算数準備にも役立つ1冊です。
 小学校入試対策 能力育成問題集3 点描写3
小学校入試対策 能力育成問題集3 点描写3
【対象年齢の目安:4歳〜】
点描写1,2とは違い、線の数が増え、とらえにくい斜めの線も多くなりますが、ある程度点描写に慣れた子供にはぜひチャレンジさせてみてください。このレベルの点描写が難なくできるようになれば、さまざまな能力の向上が目に見えて実感できるようになっているはずです。
後半では絵をモチーフとせず、複雑な線だけで構成された問題も出てくるようになります。図形として認知しづらいので、図形認識に対する能力とともに集中力も必要になってきますが、それらの能力向上には大きな効果があります。
・図形や線をとらえ
・それを頭の中でイメージして
・正確に再現する
点描写に取り組む際は上記の作業が必要になりますが、これは図形能力と密接な関係があります。これらの能力を組み合わせることにより、点描写で線を描いて図形を再現することができるのです。
ピグマリオンで重視する指先能力を鍛えるためには、点描写で必要になる運筆能力を向上させることが重要です。そのためには、まず正確に図形を再現できるように図形能力を向上させてください。
 小学校入試対策 領域別問題集4 積み木 ブロック推理2
小学校入試対策 領域別問題集4 積み木 ブロック推理2
【対象年齢の目安:4歳〜】
能力育成問題集11「積み木の問題」、能力育成問題集12、13「積み木の数1、2」が完璧にこなせるようになってから取り組みましょう。
領域別問題集4「積み木 ブロック推理2」では、選択肢から解答を選ぶのではなく、実際に自分で見えるブロックを考え、書かなくてはなりません。図だけで考えるのが難しい場合、実際にウッディブロックなどを使い、積み重ね、上、右、左、前、後と書き写させましょう。また、図はまず約束事(ブロックは同じ長さで書くなど)を決め、指導者が見本を見せてあげると書きやすいでしょう。
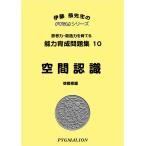 小学校入試対策 能力育成問題集10 空間認識
小学校入試対策 能力育成問題集10 空間認識
【対象年齢の目安:4歳〜】
すべての人間は、人それぞれ違う空間感覚を持っています。空間感覚は生まれもって得るものではなく、後天的に自ら創りあげていくものです。この感覚は、数や言語の基礎をなす、とても大切な能力です。まずは、空間感覚を高いレベルに育ててください。
この問題集は、平面位置の問題が特に大切です。左のサンプルの○や△を同じ位置に描き写せない子供は、空間感覚がきちんと育っていないと思われます。間違わず完全にできるようになるまで、平面位置の問題に毎日数問ずつ取り組んでみましょう。
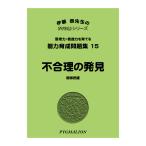 小学校入試対策 能力育成問題集15 不合理の発見
小学校入試対策 能力育成問題集15 不合理の発見
【対象年齢の目安:3歳〜】
不合理の問題は、問題の対象そのものを知らなければ、解答はできません。わからない問題があれば、図鑑を見て調べたり、実物をよく観察するようにしてください。単に紙の上だけで解答できるようになっても、それは社会で役立つような本物の知識とはなりません。日常生活の中で、いろいろなものを見たり考えたりする習慣があれば、不合理の問題はさほど難しくはありません。
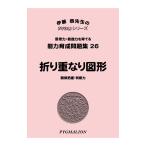 小学校入試対策 能力育成問題集26 折り重なり図形
小学校入試対策 能力育成問題集26 折り重なり図形
【対象年齢の目安:4歳〜】
「折り重なり図形」の問題は、能力育成問題集36「鏡絵」と能力育成問題集14「重なり図形」を合わせたような問題です。本書が難しい場合には、まず「鏡絵」と「重なり図形」をできるようにすれば、「折り重なり図形」も正しい答えが導き出せるでしょう。
この問題は、思考力をチェックするための問題です。思考力を正しく育てるためにも、解答の際に補助線を引いたり図形を書き込んだりしないようにしましょう。ただ単に答えが出ればよいという指導では、本当の思考力は育ちません。
 小学校入試対策 能力育成問題集29 視覚的記憶1
小学校入試対策 能力育成問題集29 視覚的記憶1
【対象年齢の目安:3歳〜】
「視覚的記憶」の問題は、表面的には種類が非常に多くあるように感じられますが、どのような問題であろうと、結局は目で見たものが脳に焼き付いているかどうかにつきます。それ以前に目の前にあっても解答できないのであれば、構成把握能力などの育成を先にしてください。
<問題集の使い方>
各問題をキリトリ線で切り離し、15〜20秒ほど見せてから解答させましょう。見せる時間は子供の能力次第で調整してください。
 小学校入試対策 能力育成問題集12 積み木の数1
小学校入試対策 能力育成問題集12 積み木の数1
【対象年齢の目安:3歳〜】
積み木を自在に分割し、集合体として瞬時に数を認識することで、四則演算のすべての基礎が育成されます。この問題は数能力全般の能力育成に効果的で、特に事象の抽象化・概念化の能力育成に効果を発揮します。問題に取り組む際は、単純に1・2・3・・・と数えさせず、数をまとまりとしてとらえる練習をさせてください。
積み木の問題・積み木の数2と一緒に取り組めば、確実に数能力がアップしていきます。無理をせず、一日数問ずつこなしていきましょう。
 【演習】小学校入試対策 能力錬成講座 年中演習10〜12
【演習】小学校入試対策 能力錬成講座 年中演習10〜12
【対象年齢:年中(4歳,5歳)】
※本テキストは、『能力錬成講座 年中』シリーズをすでに学習された方を対象にした演習問題となっております。
ご家庭で小学校入試対策をお考えの方は、まずは『能力錬成講座 年中』から取り組んでください。
【演習】能力錬成講座では、小学校受験の考査内容である「ペーパーテスト」問題をさらに学習できるよう、幅広いテーマを扱っております。本テキストを通して「ペーパーテスト」問題の強化を目指します。
『能力錬成講座 年中』シリーズ同様、お子様用の「解答用紙」と保護者用の「問題・解答」は別冊になっていますので、便利にお使いいただけます。
【ペーパーテストの例】
記憶,位置・思考,数量,構成,知識・常識,言語
【こんな方におススメ】
◎『能力錬成講座 年中』を学習された方
・小学校受験に向けて十分な準備期間をとって始めたい方
・ご家庭のペースで入試対策をしたい方
・お教室に行く前の準備をお考えの方
 小学校入試対策 領域別問題集3 積み木 ブロック推理1
小学校入試対策 領域別問題集3 積み木 ブロック推理1
【対象年齢の目安:4歳〜】
能力育成問題集11「積み木の問題」、能力育成問題集12、13「積み木の数1、2」が完璧にこなせるようになってから取り組みましょう。
領域別問題集3「積み木 ブロック推理1」は、3方面から見た形を図に描くことで、構成把握能力、図形把握能力を育成するとともに、空間能力に深い関係のある視野の広さ、つまり多方面から物事をとらえ、試行できる能力を育てることが目的です。
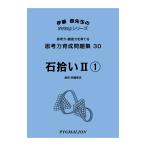 思考力パズル 思考力育成問題集30 石拾いII(1)
思考力パズル 思考力育成問題集30 石拾いII(1)
【対象年齢の目安:6歳〜】
ー江戸時代の「和算パズル」に挑戦「石拾いII」ー
○と○を一筆書きのように一本の線で結ぶ問題です。まずは、指でなぞるなどできるだけ頭の中で考えてみましょう。プリントの上におはじきなどを並べて実際に拾いながら考えてもよいでしょう。
取り組む中で、「認知スキル」「問題解決スキル」が育ちます。
【思考力育成問題集について】
ピグマリオンの数多くある問題集の中から、次世代スキルを伸ばす小学生向けの問題集をPYGLIシリーズとして選びました。
思考力パズルはルールだけ確認したら、あとは子ども自身が1人で考えて答えを出すことができるので、「1人でできた」という達成感が持てます。自信がつくので、難問に対して粘り強さ,集中力が身に付きます。
最初は簡単なので、何となくの感覚でも解けますが、後半の問題は、大人でも読み切ることが難しい問題も含まれています。
ぜひ親子でチャレンジしてみてください。
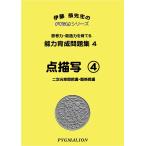 小学校入試対策 能力育成問題集4 点描写4
小学校入試対策 能力育成問題集4 点描写4
【対象年齢の目安:4歳〜】
点描写3と同様に、少しレベルの高い問題ですが、点描写1,2,3ができたら、点描写4も難なくこなせるはずです。複雑な図形や点の上を通らない斜めの線も増え、簡単な点描写では物足りなくなった子供には最適です。
前半の問題はそれほど難しくはありませんが、一本でも間違えていると正しく書き写したことにはなりません。線の本数が増えているので、解答のチェックはきちんとしてください。
前半に比べると、後半は難易度が上がります。点描写の総仕上げとして、ぜひチャレンジさせてみてください。このレベルの点描写が難なくできるようになれば、さまざまな能力の向上が目に見えて実感できるようになっているはずです。
後半では絵をモチーフとせず、複雑な線だけで構成された問題が出てきます。図形として認知しづらいので、図形認識に対する能力とともに集中力も必要ですが、それらの能力を鍛えるためには最適の教材です。
 小学校入試対策 能力育成問題集8 位置の記憶2
小学校入試対策 能力育成問題集8 位置の記憶2
【対象年齢の目安:3歳〜】
【使い方】○△×などが描かれたプリントをページごと切り離して、子供に10秒ほど見せます。それから、解答用のプリントを渡してとらえた形を描かせます。
図形の位置を記憶し、再現します。「位置の記憶1」よりマス目が増え、少し難しくなりますが、ぜひチャレンジしてみてください。
指導の初期は、○△×などの形、数と並び方のみならず、空白の部分についても、数と並び方を同時に関係としてとらえるように指導します。たとえば、詳細画像2の問題ならば「○が5つあって、その並び方は中心と四隅で、○がバツ印のように並んでいる。反対に空白の部分はひし形のように並んでいる」という具合です。
○△×などの形を一つ一つ記憶するのではなく、全体でとらえるようにしてください。
全体でとらえられるようになったら、次はまず子供にどのようにとらえるのかを言わせてみて、別の考え方やとらえ方についてもアドバイスします。ある程度こなせるようになったら、自分で考えさせて解答させればよいでしょう。
 小学校入試対策 能力育成問題集13 積み木の数2
小学校入試対策 能力育成問題集13 積み木の数2
【対象年齢の目安:3歳〜】
積み木を自在に分割し、集合体として瞬時に数を認識することで、四則演算のすべての基礎が育成されます。この問題は数能力全般の能力育成に効果的で、特に事象の抽象化・概念化の能力育成に効果を発揮します。問題に取り組む際は、単純に1・2・3・・・と数えさせず、数をまとまりとしてとらえる練習をさせてください。
積み木の問題・積み木の数1と一緒に取り組めば、確実に数能力がアップしていきます。無理をせず、一日数問ずつこなしていきましょう。
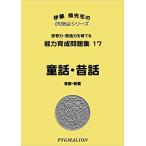 小学校入試対策 能力育成問題集17 童話・昔話
小学校入試対策 能力育成問題集17 童話・昔話
【対象年齢の目安:4歳〜】
最近、小学校受験で童話・昔話の問題がよく出題されるようになりました。この問題集は、入試でよく出題される物語と出題パターンを取り上げています。
童話・昔話は小学校受験対策だけのために学習するのではなく、言語能力の育成、特に物語的文章力の基礎作りという観点で取り組むようにしてください。そのほかに、基礎的教養として童話・昔話の知識が問われるので、ある程度は物語の内容を知っておく必要があります。
童話などの知識を問う問題が入試でよく出題されますが、これは子供の知識だけではなく、家庭での学習環境も問われているのです。子供のうちから読書の習慣をつけるために、できるだけ絵本の読み聞かせをしてあげましょう。
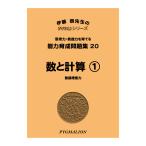 小学校入試対策 能力育成問題集20 数と計算1
小学校入試対策 能力育成問題集20 数と計算1
【対象年齢の目安:4歳〜】
数能力を育成する際に、数を数量として認識させること、つまり、ただ単に1,2,3と数えるのではなく、瞬時に数をとらえ、数をかたまりとして認識させる指導はとても大切です。
小学校1年生ぐらいまでの簡単な問題なら手で数を数えても解答できますが、このやりかたでは数を感じることはできませんし、きちんとした数能力を育成することはできません。
数と計算の問題に取り組む際は、1つ1つ数えていくような方法ではなく、2つや4つなど、数がかたまりとして認識できるように指導してください。
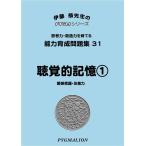 小学校入試対策 能力育成問題集31 聴覚的記憶1
小学校入試対策 能力育成問題集31 聴覚的記憶1
【対象年齢の目安:3歳〜】
記憶力の有無は、様々な能力や意欲などの有無だと考えています。
しかし、聴覚的記憶が弱い人は、記憶力というより、言語能力の不十分さが原因です。
つまり、話を前から順番に、一語一句間違えなく覚えるよりも、その内容を整理しながら聞き取る能力を鍛えることが、聴覚的記憶を向上させるポイントです。
能力育成問題集18「ことば」、能力育成問題集19「しりとり」などとの併用をおすすめします。
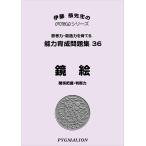 小学校入試対策 能力育成問題集36 鏡絵
小学校入試対策 能力育成問題集36 鏡絵
【対象年齢の目安:4歳〜】
問題の意味を理解させる方法としては、実際に絵や文字や数字を子供に描かせて(左右対称ではないほうがよい)、鏡に映してみることです。
左右が逆転している姿、様子を理解できるようになったら、実際に問題に取り掛かるわけですが、解答する際には「絶対違うもの」を見つける消去法や、「これが正しいならばどうなるだろう」という仮定法を使って考えるようにしてください。
 小学校入試対策 領域別問題集5 積み木 ブロック推理3
小学校入試対策 領域別問題集5 積み木 ブロック推理3
【対象年齢の目安:4歳〜】
領域別問題集3、4「積み木 ブロック推理1、2」では、積まれたブロックの見取り図を見て解答を導きましたが、領域別問題集5「積み木 ブロック推理3」では積み木が積まれた上から見た平面図を基にし、正面図と側面図を推理します。(ブロックの数は予想される最少の数で考えてください。)
この問題は、中学受験でも出題されるように、空間把握能力の発達程度を見る重要な問題です。
●図だけで解答を導くのが難しい場合は、最初は積み木を問題のように実際に積んで解答を導くようにしましょう。
●理解しはじめたら、ブロックを使わず、常に頭の中で積み木を浮かべ、上、前、左と移動してみるようにトレーニングすることが大切です。
●最少のブロックの数を正解とみなします。答えを出す前に、頭の中で描いた積み木をイメージして省けるブロックを除いていきます。
ピグマリオン 今しかできない幼児の算数シリーズ1 2才児のさんすう